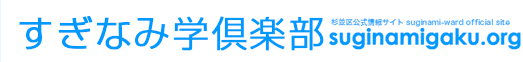大西瞳さん
風邪をこじらせただけなのに
私たちはよく「ちょっと風邪ひいちゃって…」と言う。しかし大西さんの場合、軽い話では済まなかった。風邪をこじらせ、心臓の筋肉が炎症を起こす心筋炎になってしまったのだ。このとき23歳。海外添乗員を目指し、バス旅行の添乗員として仕事を始めた矢先のことだった。
一ヶ月間意識不明に陥った結果、心臓にはペースメーカーが埋め込まれ、血流が滞り壊死してしまった右足は大腿部から切断するしかなかった。突然のできごとに現実を受け入れられず、悲嘆にくれる大西さんだったが、家族や友人たちは「よくぞ命を失わずにいてくれた」と生還を喜び励ましてくれた。そんな周囲の人たちの思いが、足を失ったことより"生きていること"に目を向けて生きる大西さんの原動力になった。
歩けるようにはなったものの
そうは言っても、寝たきりで筋肉が萎えてしまった状態からの再出発は大変だった。ベッドから起き上がることさえできない。車椅子に乗り移ることもできない。義足を作ることになったが、義足を付けている人が体を大きくゆすって歩く姿を見て、事の重大さにショックを受けた。
義足はソケット(筒)から伸びる構造で、油圧システムのターンテーブルが膝関節の役割を果たしている。そのソケットに、残っている自分の脚を入れて履く。交互に足を出して歩く際は義足にも体重を乗せるので、ソケットと自分の脚がしっくりこなければならない。しかし大西さんの場合、サイズ調整がうまくいかず、履いたときの痛みが取れなかった。もう歩けないのか。歩けなければ何もできない。でも足はもう伸びてこない。「絶望的な日々でした。」と大西さんは言う。
そんな時、ある義肢装具士が大西さんの足にフィットするよう義足を改良してくれた。そのおかげで履けるようになったが、切断した脚の筋肉が弱っていたこともあり、なかなかスムーズな体重移動ができない。それでもなんとかきれいに歩きたくて、「ショーウィンドウの前を歩くときや鏡のある場所では自分の姿を確認していた」そうだ。"義足を付けている自分"をまだ肯定できない大西さんだった。
すると義肢装具士が、自身が代表を務める切断者スポーツクラブ『ヘルスエンジェルス』を紹介してくれた。さまざまなタイプの義肢をつけた人たちが、陸上競技、スキー、アーチェリー、トライアスロン、カヌー、自転車など、いろいろなスポーツに生き生きと取り組んでいるクラブだ。「走れるようになるときれいに歩けるようになるよ。」と言われ、陸上チームを見学に行った大西さんは目を見張った。「足を交互に出して走っている。しかもあんなに速く。」中学高校時代に中短距離走の選手だった大西さんは、自分も挑戦しようと決めた。
▼関連情報
ヘルスエンジェルス(外部リンク)
コンプレックスが消えた
競技場へは普通の義足に靴を履いて行く。トラックの横で板バネのついたスポーツ義足に替えるのだが、大西さんは最初のころは何となく恥ずかしくて目立たないように替えていた。だが、周囲の選手は談笑しながら義足を外し、何の気負いもなく、あっけらかんとつけ替えている。何より、走っているときに義足は隠しようがない。大西さんからコンプレックスが消えていったのは自然なことだった。
大西さんは振り返る。「私は本物の足に見えるようにすることばかり考えていました。でも義足を付けて走っている先輩たちはカッコ良かったんです。義足が当たり前という環境で、私も義足を自分の"ちょっとカッコイイ足"と思えるようになりました。」
中学高校時代の部活動で走っていた大西さん。再び走れるようになったことで、切断という障がいを「乗り越えた」と思えたそうだ。板バネを付けて走ることを「軽トラックからポルシェに乗り換えた感じ」と表現する。
練習に打ち込むようになって、記録は面白いように伸びていった。走るときに身体がぶれないよう体幹トレーニングを欠かさずに行ない、さらなる記録更新を目指す。体重がうまく乗らなかったり汗をかいていたりすると、義足が脱げて転ぶこともあるが、もう大西さんはひるまない。
「障がい者」の概念を超えて
そうなると今度は義足を人に見せたくなる。同じ作るならきれいな物を…と、大好きな海を思わせる鮮やかなブルーにハイビスカスを描いた義足をオーダーした。気が付けば、お気に入りの義足を持つ仲間が増えていた。「私たちの義足を見てもらおうよ」と、路上ファッションショーをした。『切断ビーナス』という写真集にも参加し、障がい者の"暗い"というイメージを変えたと話題を呼んだ。義足が身体の機能を補うだけでなく、チャームポイントとして人間関係を広げるきっかけにもなったのだ。
義足をギャグにしてしまう余裕もできた。取材のとき、「こんなことできるんですよ」と足を回転して見せてくれた。「こうすると日本の人たちは見てはいけないものを見たような顔をしますけど、外国の人にはウケるんです。」と屈託が無い。
ここまで明るく前向きな大西さんに戻れたのは周囲の力も大きい。落ち込んでいるのを言葉で励ますだけでなく、バリアフリーの場所を探し、同行し、チャレンジする機会をつくってくれた。さらに大西さん自身も「義足になったからできないとは言いたくない」という負けず嫌い。もちろん海外旅行も再開し、ヨーロッパの石畳の坂道も制覇した。
「やってみれば案外できちゃうものです。だから、最初からダメだと諦めないでください。工夫すればできることがたくさんあるんです。どうせ生きるなら楽しく生きたいじゃないですか。」今では「あ、義足だったんだ」と気づくことがあるくらい、と笑った。
義足だからこそできること
義足を必要とする身体になったからこその出会いがあり、知ることのできた世界がある。「今、もしも足が元通りになったら困っちゃいますよ。失うものが多すぎて。」と言う表情には、今の自分が大好きだという気持ちがあふれていた。この世の終わりと思えた障がいが、生きていく方向を変えたのだ。しかも、大西さんの言葉を借りれば「ラッキーな方向」に。「だって、オリンピックは無理だけど、パラリンピックなら狙えるんですよ」。2015(平成27)年4月現在、大腿切断者クラスの100m、200m、幅跳びの日本記録を持つ大西さんは本気だ。相棒を見るような目でスポーツ義足を見つめた。
これからは、切断・義足に不安を持っている人や義足を付け始めた人のところへ出向いて、自らの経験を話していきたいと言う。「障がいを持つことは、確かに不便なこともありますけど、マイナスばっかりじゃありません。私を見てください。」と。
では、障がいを持たない人や社会は、持つ人とどう接すれば良いのか聞いてみた。「障がい者と健常者を分けないで欲しいんです。見ないようにするのではなく、見て、『何か手伝いましょうか』と軽く声をかけてください。助けて欲しければお願いするし、必要がなければ大丈夫ですよと応えますから。」
誰もが自然に助け合えるよう、子供の頃から障がい者と触れ合う機会を作り、ヘルプの仕方も学んでいきたいものだ。
取材を終えて
インタビューの場所に自分で車を運転して現れた大西さん。さっそうと下りてきてハッチバックを開け、スポーツ義足を取り出した。小柄な大西さんには一抱えもある。持たせてもらった。「意外と重いんですね」と言うと、「本物の足はもっと重いですよ」と笑った。彼女に「障がい者」のマイナスイメージはない。困難にぶつかった時、心が立ち直るためにスポーツが果たす役割の大きさを改めて感じた。壁を乗り越えて自分を好きになれた人は、すがすがしい。パワー全開の大西さん。次のパラリンピックで選手としての笑顔を見たい。瞳さん、応援しています!
大西瞳 プロフィール
1976年杉並区生まれ。方南町在住。東京都立杉並高等学校卒業後、バス旅行の添乗員をしていた2000年に、風邪がもとで心筋炎になり右大腿部を切断、ペースメーカーを入れた。その後、「義足のアスリート」として陸上競技を始める。2015年4月現在、大腿切断者クラスの100m走で17秒41、200mで37秒85、幅跳びで3m11の日本記録を持つ。都内の区役所に勤務しながら、切断者スポーツクラブ『ヘルスエンジェルス』のメンバーとしても活動。障がい者の情報バラエティテレビ番組の司会者を務めるなど、多方面で活躍している。
<追記>
大西さんは2016(平成28)年9月に行われたリオパラリンピックに出場。幅跳びで自己ベストを更新し6位入賞(3m58)、100mで8位入賞(17秒51)を果たした。障がいを持つスポーツ選手は現役の期間が長く、記録を伸ばし続ける人が多い。自分の限界に挑戦する姿は、見る人すべてを勇気づける。大西さんのさまざまな活動によって、心のバリアフリーも進んでいくだろう。
-2016年10月3日 加筆-
2016(平成28)年11月24日、大西さんに「杉並区スポーツ栄誉章」が授与されました。
-2016年12月12日 加筆-
DATA
- 取材:阿佐ヶ谷あけみ
- 撮影:syaeidou
写真提供:大西瞳さん、加藤詩生さん、藤田ゆうすけさん - 掲載日:2015年05月25日
- 情報更新日:2016年10月03日