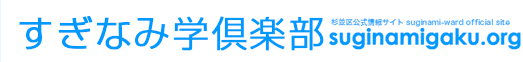炭屋
新天地荻窪で店開き
家庭用燃料販売の歴史は、かつての日々の家庭生活を支える生活必需品、炭の販売の歴史でもあったが、1955年(昭和30年)頃をピークに、家庭用燃料としての炭の役割は灯油に移行し、商売の内容も変わり、さらに近年では、灯油からガス、電気への移行で、事業者数も減少している。杉並区内の二つの同業者組合も、2008年(平成20年)に解散した。創業以来、荻窪の炭屋の草分けとして、灯油のみならず、現在も炭にこだわりつづける、久我屋商店二代目、湯澤進さんに、炭屋商売についてうかがった。
久我屋商店の創業は関東大震災から2年後の1925年(大正14年)のことだ。湯澤さんの父、若次さんは、栃木県上都賀郡加蘓村久我(現在、栃木県鹿沼市)から上京、渋谷駅前の炭問屋久我屋で修業。一番番頭を勤めたのち若くして暖簾分けした。開業の地に選んだのは荻窪、くしくも火の神を祀る秋葉神社のあった四面道だった。震災の被害を目の当たりにした東京市中の人々が続々と荻窪に移住してきた時期だった。
「最初はかなり遠くまで売りにいっていたんじゃないかな。あとは酒屋に卸していた。実際に売っていたのは酒屋だよ」
生活必需品であった炭は、それまで荻窪では酒屋が販売していた。その販売を取り仕切る問屋としては、荻窪の草分けだった。
「記録は残ってないけどね。初代の八丁の商店街の会長だったと聞いてるよ」
湯澤さんが子どもの頃には若い衆が何人か住み込みで働き、炭屋の仕事に従事していた。
「土手に水溜まりがあちらこちらにあって、おたまじゃくしをとったね」
当時は中央線が高架になる前で、家の近所には線路の土手がつづいていた。土手の一本松と呼ばれた松の古木のあたりでよく遊んだという。写真は、1935年(昭和10年)の久我屋本店の初荷の記念写真。現在の渋谷駅東口広場だ。
「おやじが写ってるんだよ。半天をはおってさ。東京でも久我屋の看板を掲げているのは、もううちだけしか残ってないんだよ」
炭屋の繁盛振りを後世に残す記念の一枚だ。
炭がささえた日々の生活
湯澤さんが仕事を始めたのは1951年(昭和26年)、高校卒業後、18歳の時だ。戦後の混乱期をへて、荻窪の生活がもとに戻り始めた頃だ。
「長男だし、継ぐことは小さい頃から自覚していたからね」
中学の頃から仕事を手伝っていたので、お客さんも顔なじみで、仕事を始めるにあたっての違和感はなかった。配給統制が終わった頃には、荻窪の炭屋は58軒にまで増えていた。
「配達だよ。毎日そのくりかえし。もう問屋なんかやってなかったよ。注文受けてね。58軒もあったから、それぞれ分担みたいなもんでね。うちは、ここからずっと西、上荻のほう、1km四方くらいの中だね、・・・はじめは、自転車とリヤカーだよ。何軒分しか積めないから、配達にいってはもどり、またでかけて」
扱っていた炭は、主に、調理用、暖房用、炊事用の炭だ。調理は炭と七輪、暖房は炭と火鉢と決まっていた時代だ。
「月単位でどの家も買うんだよ。そうねえ、一般家庭で、月に4、5俵かな。16部屋もあるようなお屋敷もあったんだよ。女中さんが3、4人いてさ。そういうとこは、月に10俵とかね」
冬支度に入る季節には、200俵くらいの炭俵が店に山積みになったそうだ。
炭に関する知識は、親から伝え聞いて自然と覚えた。
「東京で売っていた炭は岩手だよ。あと福島と栃木。それと青森、八戸、一戸あたりの炭だね。炭の質は火力と火持ちだね。密度のちがいなんだよ。高い炭は暖房用、カシとクヌギ、上質品だね。カシというと馬目カシ。紀州の海岸ふち、潮風のあたるとこのがいい。紀州備長炭だね。安い炭は調理用。火持ちがいい。ナラとか。それと雑っていってもっと安い炭もあった。桜炭といって、クヌギの中でも上級品は、茶道用だね、薪も扱っていたよ。炊事に炭なんか贅沢で、使うひとはあんまりいなかったよ。薪だよ。毎日のことだし、だれも出費はおさえたいからね」
炭への出費が生活費の中で大きな比重をしめていた時代の話だ。
「石炭も扱っていたよ。ダルマストーブ、学校に入れていたよ。コークスは使わなかった。石炭、石炭はすぐに火がつくからね」
炭と炭を売る日々のひとこまひとこまがよみがえる。
炭屋さん兼灯油屋さん
「炭の需要が一番多かったのは昭和30年くらいかな、あとは灯油だね。昭和40年頃からは灯油があがってきた」
戦後、灯油を使った石油コンロがおもに炊事用に普及した。石油コンロから開発された石油ストーブがさらに灯油の需要を増やすことになった。出費としては炭とおなじく低価格で、扱いがなにより便利だったからだ。湯澤さんも次の時代の商売に備え、27歳の時に、すでに取り扱い資格を取得していた。小売業の構造的変化に対し、専門性を活かす道を選んだ。
1万リットルの地下タンクをおもいきって入れたのは1969年(昭和42年)のことだ。
「ドラム缶で仕入れて分けて売っていた。その後は18リットル単位になって、荻窪警察署のとなりまでその都度、取りに行っていた。おやじが亡くなって全部一人でやってたから、大変でしょ。それにタンクがあって貯蔵があれば店の売りになるしね。ガソリンスタンドなんてない時代だからね」
売れた時は、一ヶ月でタンクローリー10台分売れたという。
「今は、出費でいうと、灯油1、ガス3、電気5くらいの割合だね。電気で熱をおこすのはまだまだ高いね。電気カーペットと灯油ストーブを使うのが出費からしたら理想なんだけどねえ」
ガスと、さらにガス暖房の普及が灯油の売れ行きに深刻な影響を与えはじめて10年近くが経過している。
「燃料店なんてもともとないよ。炭屋のことだよ。炭は売ればいいんだからさ」
灯油に商売の主力を移しながらも、あくまでも炭屋にこだわりつづけてきた。灯油に地位を奪われた炭がよく売れた年があった。1973年(昭和46年)から翌年にかけてのオイルショックの頃だ。灯油不足の非常時、たよりになったのは炭だ。
「正直、炭が動いたのはそれだけだね。茨城からも問い合わせがあってね。在庫は空っぽになっちゃったよ。あの時は、七輪も売れたねえ」
地下タンクのおかげて灯油もどんどん売れたが、炭まで売れるとはおどろきだった。太古の昔から伝わる、火をおこし使うための生活必需品としての炭の存在意義が大きくクローズアップされた時代の一コマだった。
火鉢でお客さんを迎える冬の店先
「今度は、大型店舗同士の競争でしょ。消費者にはいいけどね」「回転のいい商売でないと経営はむずかしいね。いいのは、クリーング屋とかパーマ屋かな」「副収入あるとこじゃないときびしいよ。だけど副収入あてにしてちゃ商売じゃないよ」。長年にわたる個人商店の経営の苦労は並大抵のものではなかった。「跡なんか継がせない。息子なんかに絶対させない」。あえて二人の息子さんには継がせず、勤め人になる道を選ばせた。
「需要がなければ売れないよ」と商売っ気を見せない湯澤さんだが、恒例の店の冬支度には、毎年火鉢を用意する。「お客さんが入ってきて、喜ぶんだよ。懐かしいってね。炭はさ、暖かさが柔らかいんだよ。強くない」。お客さんとのコミュニケーションを第一に考える、商いのプロらしい気遣いだ。
「今は、炊飯にいれたりね。竹炭だね。湿気とりとか」「調理用っていっても、焼き鳥とうなぎだね」「バーベキュー用とか、災害時の備え用とか、一時売れたけど、今はそうでもないね」「桜炭といっても使うのは初釜くらいじゃないのかな」。炭の消費動向も気にかける。
「サンマはさ、七輪で二匹焼くのがいいんだけど、うちは三人だからさ。二匹づつ焼いて、一匹は近所にあげてんだよ。美味しいって喜ばれるよ」。炭の生活を自ら継承している。
湯澤さんの気掛かりは、役員を務める荻窪八幡神社と南荻窪天祖神社の秋祭りの動向と有志でおこなっている旧秋葉神社の秋の神事、それと八丁の商店街の主催するバーベキュー大会だ。「子供たちに、炭を使った火のおこしかた、炭で焼いた美味しさを伝えたいね」「創業100年といったら大変だよ。90だよ。90すぎちゃうよ」。久我屋商店はさらに創業100年をめざす。
DATA
- 最寄駅: 荻窪(JR中央線/総武線) 荻窪(東京メトロ丸ノ内線)
- 取材:井上 直
- 撮影:NPO法人TFF
- 掲載日:2009年08月27日