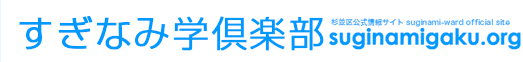天沼熊野神社

八咫烏(やたがらす)が描かれた諸願成就の絵馬
奈良時代の創立と伝えられる、旧天沼村の鎮守
荻窪駅から北東に徒歩約12分、鳥居の両側にちょうちんが並ぶ天沼熊野神社(あまぬまくまのじんじゃ)。旧天沼村の鎮守で、伊邪那美命(いざなみのみこと)を奉っている。創立は768(神護景雲2)年と伝えられ、昔は「十二社権現」と称していた。「熊野神社」と名称を改めたのは、明治に入ってからのことだ。
お守りや絵馬には、和歌山県にある熊野三山に祭られている熊野大神(くまののおおかみ)に仕える存在として信仰されていた八咫烏が施されている。鳥居のそばにそびえる木は、熊野神社のご神木とされるナギの木だ。宮司の渡辺さんは、「この木は、近隣の方がここにあった方がふさわしいと1995(平成7)年にくださいました。ほかにも、鳥居の前の階段を施工者のアイデアを取り入れて緩やかにするなど、常に皆さまからのご意見を大切にするようにしています」と話す。
境内には直径2mはあろうかという杉の切り株が展示してある。これは鎌倉時代後期の武将、新田義貞(にったよしさだ)が戦勝を祈願して植えたといわれ、その後、鎌倉幕府を倒したため、「出世杉」と呼ばれている。
例大祭は例年、6月最初の日曜日を基準に、土曜と合わせて2日間行われる。「夏の暑い時期を避けて行っています。最後に演じられる神楽舞は、通常は神様に向かって舞うのですが、この日だけは皆さまを神様と見立てて舞います。だから神々しいのです」と渡辺さん。
長い歴史を受け継ぎながら、今も地域の鎮守として人々に寄り添い続けている神社だ。
年末年始の催し物(2025年12月-2026年1月版)
12月30日 18時(年越しの祓、または師走の祓)
1日の午前0時より、17時まで社頭にて参拝者のお祓い。(午前3時より午前9時は休憩)
1日の午前0時より、お札や注連縄(しめなわ)のお焚き上げ、無料の甘酒の振る舞いがある。(甘酒はなくなり次第終了)
DATA
- 住所:杉並区天沼2-40-2
- 電話:03-3220-7866
- FAX:03-3220-7866
- 最寄駅: 荻窪(JR中央線/総武線) 荻窪(東京メトロ丸ノ内線)
- 公式ホームページ(外部リンク):http://www.amanumakumano.org/
- 取材:おおつちさとべえ、TFF
- 撮影:TFF
取材日:2015年05月28日、2025年06月12日 - 掲載日:2025年08月27日
- 情報更新日:2025年12月02日