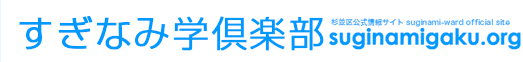- トップページ
- 歴史
- 戦争のつめ跡・戦争体験
- 【証言】眞島フユコさん
【証言】眞島フユコさん
東京の空襲を逃れて
広島に原爆が投下された時、私は21歳でした。
東京の旧制専門学校卒業後、東京の空襲が激しくなり、実家である広島に帰ることになったのですが、交通手段であった国鉄(現JR)の東海道線は各地の空襲によってところどころ寸断され、途中で何度か乗り換えしながら、やっとの思いで広島の実家へとたどり着きました。
広島では広島中央放送局(現NHK広島放送局)の技術部に配属され、1日おきの24時間勤務をしていました。それまでは男性が主だった技術部も、戦地に赴く人が増えて人手不足となり、女性も携わることになったのでした。実家から職場までの間には、海軍や陸軍の第5師団などの駐屯地があり、空襲を逃れるための疎開として帰ったはずの実家も、危険区域に指定されていて、空襲のサイレンは日々やむことはありませんでした。
8月6日朝、それは突然の出来事だった
8月6日の前日から、私は泊りがけの勤務で放送局内にいました。そして、8月6日の朝。空襲警報のサイレンもなく、原爆投下は突然の出来事でした。私は録音室にいましたが、突然体が吹き飛ばされて、そのまま気を失ってしまいました。青白い光を見たような気がして、ああ爆撃だとぼんやり思ったことを、かすかに覚えています。身につけていた時計は午前8時15分を指して止まっていました。一度、誰かに名前を呼ばれて気づいたものの、ぼおっとしたまま、またすぐ気を失ってしまったようです。私に今も命があるのは、被爆時鉄筋コンクリート造りの放送局内にいたからで、実家にいたならば命はなかったでしょう。その時自宅にいた母は、あの原爆によって命を落としました。
左手をひどく負傷したことは分かったものの、それを気にすることもないまま、放送局から避難場所へと向かったのですが、被爆してから避難場所にたどり着くまでの間の記憶は、とても断片的なものです。記憶をたどれば、気づいた時には大田川という川べりを歩いていました。どこをどう歩いたのか、どれぐらいの時間が経過していたのかはさっぱり分かりません。放送局内で同じように被爆した人が助けて歩かせてくれたのですが、それがどなただったのかも、今でも思い出せないのです。川の対岸からは火の粉がパチパチと飛んできて、流れの中にはやけどの熱さに川に飛び込んだ多くの人たちが、助けを求める声を上げながら、ひき潮の速い流れにどんどん流されていました。泳ぎに自信があったので、いざというときは川に飛び込むつもりでいましたが、とにかくたくさんの人が大変な勢いで水に流されてゆくので、なす術もありませんでした。その日、ポタポタと大粒の雨が降っていたことをぼんやりと覚えていますが、それが黒い雨だったかどうかは、分かりません。
凄惨たる焼け野原となった広島市内
日が暮れるころになって、同僚の女性二人と出会い、3人で広島駅の方に向かいました。駅の裏手には東練兵場があり、そこにあるバラック小屋は爆撃で負傷した人で足の踏み場もありませんでした。呉の海軍病院から救助隊が到着していましたが薬などほとんどなく、ヨードチンキと赤チンだけ、という有様でした。私を見た救助隊員が、これはひどい、といって目だけが出る大きなマスクと、負傷した左手に添え木をし大きな三角巾を吊るしてくれました。そのときまで私は、痛みや出血があったにもかかわらず、自分が怪我をしていることに気がつかなかったのです。そういえば同僚に声をかけたとき、私の顔にはりついた髪の毛をかき分けながら、「誰?」と言っていたのですが、私は自分の顔がどんな状態になっているのかなど、考える余裕もありませんでした。小屋の中にいる負傷者のやけどのひどさや、お水をください、水、水、という声と人いきれで胸が苦しくなり、私たちはすぐにそこを出ました。
練兵場の上にある山の方は、二葉の里と呼ばれている地だったのですが、そこでは早くも炊き出しが始まっていて、おにぎりを1つもらいました。おにぎりを食べようとすると、上の前歯が2本抜け、かろうじて歯茎にくっついてたれ下がっている状態だったため、かぶりつくことはできませんでした。6日の爆撃から、けがをしたまま何も飲まず食わずで歩き続け、やっと7日の朝に手にしたおにぎり。しかし私は、けがの痛みも、空腹やのどの渇きなども何も感じずにいました。私の神経は、正常ではなかったのでしょう。
とにかく自宅に戻ろうと思って、一人家を目指したものの、あたり一面焼け野原で、道なき道を裸足で進み、着いてみると家は焼失して防空壕の木扉がブスブスとくずぶっていました。仕方がないので母の実家の田舎に行くべく電車賃を会社で借りようと、放送局目指し路面電車の線路をたどって向かいました。黒こげになった電車とそこに乗っている人々、自動車のドアを開けようとした姿のまま黒こげになっている人、そして無数にたかるウジやハエ。そんな光景を目の当たりにしながらも、何の感慨もなく眺めて局へ着き、そこで初めて市全体が爆撃でやられたことを知ったのでした。
「被爆」という現実
そうして母の実家を目指したが、途中どんなことがあったのか、よく覚えていません。とぼとぼ歩くうち叔父の家を知る人に出会い、迎えに来るよう伝えてあげると言われ、そして叔父が迎えに来てくれました。田舎の医者に連れていかれましたが、そこも重病人であふれ、やけどの膿は夏の暑さで臭気を発し、そこに寄生する無数のハエは黒々と飛びまわり、目を覆いたくなる光景でした。その二日後に父も叔父のところにやってきましたが、爆撃後初めて会う私の姿に驚き言葉を失い、私と視線を合わせようとしませんでした。皆の消息を聞くと、母は行方不明、姉は腕を負傷したがまあ元気だからすぐにこちらによこす、と言ってまた広島市内の焼け野原に帰ってゆきました。後で聞いた話によれば、その時父は「ふた目とは見られない傷を受けている。生きていてよかったのかどうか…」と漏らしたそうです。それを聞いていた姉は、覚悟していたものの、再会した時には変わり果てた私の姿に涙を流し、私はなぜかおかしくて、意味もなく血糊で顔を引きつらせながら笑っていました。
爆撃から二週間ほどして、私は初めて自分の顔を鏡で見ました。両目はクマどられて腫れ上がり、上の前歯は2本垂れ下り、腫れ上がった唇の右側はささったガラスを無理矢理抜き取ったために亀裂が入っていました。そのお化けのような姿が自分であることをにわかには信じられず、茫然自失でした。なぜ、死ななかったのかと…。私の面影を取り戻すまでには、半年の月日が必要でした。その後、傷口から黴菌が入って敗血症寸前だった私の左腕は、大阪の放送局から派遣された医師と薬のおかげで切断を免れました。同じように広島市内の逓信局の勤務中に被爆した姉は、東京からの医師団によって白血球が異常に多いことを発見され、ビタミン注射を打ってもらい死なずに済みました。当時61歳だった父は、焼け野原の中、焼け跡を掘り返し、行方不明となった母を尋ね歩き、その結果3か月にわたる下痢と、体のあちらこちらに細胞破壊によるおできといった原爆症の症状を手当する術もなく、被爆して3ヶ月後の11月にこの世を去りました。さぞかし無念だったことだろう、と今も思います。
新型爆弾と発表したまま、その正体については何の説明もなく、多くの広島市民が家族の行方を探して放射能を吸い、原爆症となって無為に死を待つのみで死んでゆきました。なぜ原爆だと、なぜ放射能だと発表してせめて広島市内の立ち入り禁止をしなかったのか。それを思うと、今も悔しさがこみ上げます
忘れてはいけない「原爆投下」という歴史
8月15日正午の終戦詔勅は、ラジオの雑音がひどく、その言葉が断片的に聞き取れる程度だったので、集まった人々と、これは戦争が終わったということなのか、と確かめ合いました。戦争が終わった。そのとき私に一番最初に混み上げてきた感情は、安堵ではなく、強い悔しさでした。なぜもう少し早く終わらなかったか。焼けてしまった広島、我が家、家財道具、そして母…。負けたことが悔しいのではなく、ほんのわずかな時間の差で無意味に失ってしまった全てを思い、悔しくてなりませんでした。
終戦後60年、私は自分が被爆したことを家族にさえも打ち明けずにいました。忌々しい記憶だったから、ということもあるでしょう。思い出したくない過去でもあったからでしょう。
しかし「原爆」という歴史を知る人は、年々確実に減っています。被爆という現実は、私の家族や多くの人々の命を奪っただけでなく、今も多くの人々の健康や生活を脅かし続けています。
以前、とある方から、今の大学生の中に日本に原爆が落とされたことを知らない学生がいる、と聞かされて愕然としました。人々に残る記憶だけでなく、原爆という悲しい事実さえも薄れていくような危機感を覚え、伝えることの大切さを感じます。核が人類の破滅をもたらすことを、決して忘れてはならないのです。
DATA
- 取材:野上優佳子
- 撮影:NPO法人チューニング・フォー・ザ・フューチャー
- 掲載日:2008年08月13日