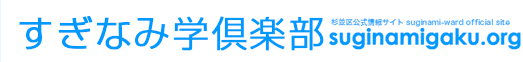- トップページ
- ゆかりの人々
- 著名人に聞く 私と杉並
- 有吉玉青さん
有吉玉青さん
思い出が息づく街、杉並
私は生まれも育ちも杉並で、今も住まいは杉並です。思い出は街に染み込んでいて、時代と共に様相は変わっても、その場にはっきりと残っています。この場所で母(作家、故有吉佐和子さん)や祖母がこう言った、ここで怒られたなどと、街角は懐かしい思い出でいっぱいです。
忘れられないのが、青梅街道沿いにあった古道具屋さんのことです。私が小学生の頃、昭和40年代後半で五日市街道が整備される前ですね。帰宅途中にお手洗いに行きたくなり、老夫婦が営んでいる古道具屋さんでお借りしました。珍しい物が置いてあり、老夫婦が親切にしてくださったことから、また訪ねたくなり、そこでお手洗いを借りるのがマイブームになってしまいました。その古道具屋さんでお手洗いを借りるのは、なんとクラスでもはやりだし、「今日は私とあなたの番よ。」と仕切る子まで現われたんですよ。お店はもうありませんが、お店のあった場所を通りかかると思い出します。
研究者志望から執筆業へ
早稲田大学の哲学科を卒業後、東京大学の美学藝術学科に3年次より学士入学しました。当時は研究者を目指していて、まだ文章は書いていませんでしたし、まして作家になろうなどとは思いもしませんでした。
母が急逝した2年後の1986(昭和61)年に、出版社から母に関するエッセイの依頼を受けて書いた『「恍惚の人」の頃』が初めて活字になった文章です。当時はワープロがなかったので、肉筆の文字が活字になり、うれしかったことを覚えています。その後、東京大学の大学院在学中の1989(平成元)年に、母の思い出を綴った書き下ろし『身がわり-母・有吉佐和子との日日』(以下『身がわり』)を発表し、坪田譲治文学賞(※2)をいただきましたが、後のことは考えていなかったのでデビュー作という意識はなかったです。
小説を書いてみようと思ったのは、アメリカのニューヨークに留学する前に滞在していたボストンにいた時です。異国の生活の中で感じたことを、文章で表現したくなりました。そして帰国後、1994(平成6)年に、初めての長編小説『黄色いリボン』(※3)を書き下ろしました。研究者になるという夢は挫折してしまいましたけれど。
(※1)『恍惚の人』:1972(昭和47)年刊行の有吉佐和子さんの小説。
▼関連サイト
すぎなみ学倶楽部>文化・雑学>読書のススメ>『恍惚の人』
すぎなみ学倶楽部>文化・雑学>読書のススメ>処女連祷
(※2)坪田譲治文学賞:1984(昭和59)年に岡山市が制定した文学賞。大人も子供も共有できる優れた作品に与えられる。
(※3)『黄色いリボン』:幻冬舎より刊行。のちに文庫化。湾岸戦争ただ中の不穏な空気の漂うアメリカ、ボストンで留学生活を送る若者の心情を描いた作品。
大切な作品、『身がわり』と『ソボちゃん』
執筆活動の原点 『身がわり』
『身がわり』は、女性作家十三人展(※4)に出品する資料の整理をするために大学院を休学している間に執筆しました。当時は祖母も亡くなって寂しかったので、書くことで救われもしました。
母が亡くなってから日記をつけ始めて、仕事で留守がちだった母とも多くの思い出があることに気付きました。共に過ごした20年間が物語性のあるものに思えてきて、私にとっての「母と娘の物語」として書いてみたくなりました。今読むと、ここまで書くことはなかったという部分があって恥ずかしいです。当時は書くことで精一杯で、どう読まれるかにまで考えがいっていませんでした。それが今との違いです。
25年の執筆活動の結晶 『ソボちゃん』
『ソボちゃん』(※5)には、執筆活動で多忙な母に代わり、私を育ててくれた祖母との思い出が詰まっています。祖母は、私が一番尊敬する女性です。祖母が戦前に暮らしていたインドネシアを取材してから書こうと思っていたのですが、けがをしてなかなか行けず、書き終えて本になったのは2014(平成26)年。構想から時間がかかってしまいました。
私は、祖母に家事から家計まで任せきりの母に批判的で、普通のお母さんに憧れていました。祖母はかわいそうだと。でも、自分自身も書きながら年を経てきたことで、わかりました。母は家のことをする時間はなかったし、祖母が母に尽くしたのは親の愛情からだと。今は、祖母がいたから母は書けたのだと思っています。
(※4)女性作家十三人展:1988(昭和63)年10月20日より東京・池袋の東武デパートで開催された。樋口一葉に始まる明治以降の日本を代表する女性作家13人を紹介。有吉佐和子さんもその一人。
(※5)『ソボちゃん』:平凡社より刊行。最愛の祖母の思い出を中心に綴られた、祖母、母、娘三代にわたる有吉家の物語。
杉並生活、楽しんでます
杉並は、居心地が良くずっと住み続けたい所です。生まれた時からずっと住んでいるので、別の場所との比較はできませんが、それでも杉並が一番。自然に自分の一部になっているという感じですね。大人になって行動範囲が広がってからは、ますます愛着を感じるようになりました。
次々にできる新しいお店、昔の雰囲気を残しながら魅力が増していく路地、阿佐谷七夕まつりや東京高円寺阿波おどりなどのイベントの盛り上がり。素敵なことがいっぱいです。創作のヒントにもなりますね。2002(平成14)年に発表した小説『キャベツの新生活』には、アパートが多いのに気づいたことがきっかけで東高円寺が登場します。
外食するなら、おいしいお店がたくさんある地元です。飽きることがありません。買い物も地元のお店が多いですね。実は私、昔からポイントやクーポンが大好きで、使える地元のお店でせっせとためています。ポイントアップデーにしか買わずに、少し遠くてもポイントのある店を利用するとか、ポイントのために自分を律してがんばります。全部ポイントで買い物できた時は、すごく得をした気分で幸福感でいっぱいです。
書いて、教えて、更新していく
書くことには、考えが形になっていく喜びがあります。エッセーは自分がわかったことを人に伝えるもので、小説は自分がわからないものをわかろうとする試みです。だから小説の方が素がでますね。2012(平成24)年刊行の『美しき一日の終わり』(※6)では、初めて登場人物の人生を長期的なスパンで捉えた作品に挑戦しました。以前から温めていて、書ける時を待っていた作品です。
また、2008(平成20)年より大阪芸術大学で文章表現を教えています。教えることは自分の勉強になり、学生からは良い刺激をもらっています。私が母を亡くした頃と同じ年代の学生たちを見るにつけ、自分もあの頃はこんな感じだったのかなと思ったり、母や祖母の心配は当然だったと、今になって納得したりしています。
昔書いたものを読まれるのは恥ずかしいですね。昔と今では考えていることは違うのに、読者にとっては区別はなく、過去の私が今の私だと思われるような気がするので。情報は更新されていきますし、それが生きていることだと思います。
2014(平成26)年は母の没後30年で記念復刊や文学展など、母のことに専心した一年でした。一段落したこれからは、たくさんある書きたいことの中から、何かがフッと立ち上がるのを待って書いていこうと思っています。
(※6)『美しき一日の終わり』:講談社より刊行。互いへの想いを胸に秘め続けた男女の55年を、時代の流れと季節の移ろいを背景に端正な文章で描いた作品。2015(平成27)年に文庫化。
取材を終えて
知的な雰囲気を漂わせている方。第一印象は、著作を読んで想像していた有吉玉青さん像とピタリと重なった。言葉を選んだゆったりした口調の受け答えに、有吉さんの人柄が感じられて、心地よい時が流れた。著作を読んだことに対して感謝の言葉を何度もいただいたのには恐縮してしまった。杉並っ子として生活を楽しむ有吉さんの意外な一面には大爆笑。手持ちのポイントカードを見せてくださるに至り、距離が一気に縮まり、親近感が増した。有吉さんは、まさに「メイドイン杉並」の作家。これからも杉並を舞台にした作品を読んでみたい。
有吉玉青 プロフィール
1963年、作家の有吉佐和子さんの長女として杉並に生まれる。1984年大学3年の時に、有吉佐和子さんが急逝する。東京大学大学院在学中の1989年に、有吉佐和子さんとの思い出を綴った処女作『身がわり』を刊行。坪田譲治文学賞を受賞する。1993年、ニューヨーク大学大学院留学を終え帰国後、本格的に執筆活動を開始。1994年に初めての長編小説『黄色いリボン』を発表。以後、小説、エッセイと幅広い執筆活動を行い、2014年、最愛の祖母への想いを描いた『ソボちゃん』で注目を集める。2008年より大阪芸術大学教授を務めている。
DATA
- 取材:村田理恵
- 撮影:TFF
- 掲載日:2015年06月29日
関連記事
History 歴史
- 杉並の変遷
- 記録に残したい歴史
- 【証言集】中島飛行機 軌跡と痕跡
- 【証言集】アンネのバラ 咲かせ続ける平和の願い
- 【証言集】杉並の養蚕と蚕糸試験場
- アニメのまちができるまで
- 杉並名品復活プロジェクト
- 【記録集】杉並にも公民館があった
- 杉並区に残る戦争のつめ跡
- 【証言集】戦争体験
- 「杉並町報」で知る昭和4年の杉並
- 歴史資料集
- 杉並の地図と地名
- 道具に見る昭和の暮らし
People ゆかりの人々
- 著名人に聞く 私と杉並
- 杉並の偉人
- 杉並の文士たち
- 道を究める
- 芸術家たち
- 教育を支える
- 地域をつなぐ
- スポーツに携わる
- 経営者・起業家
- 【アーカイブ】杉並の著名人に聞く
- 【アーカイブ】杉並の人々
- 【アーカイブ】すぎなみ人 とっておき物語